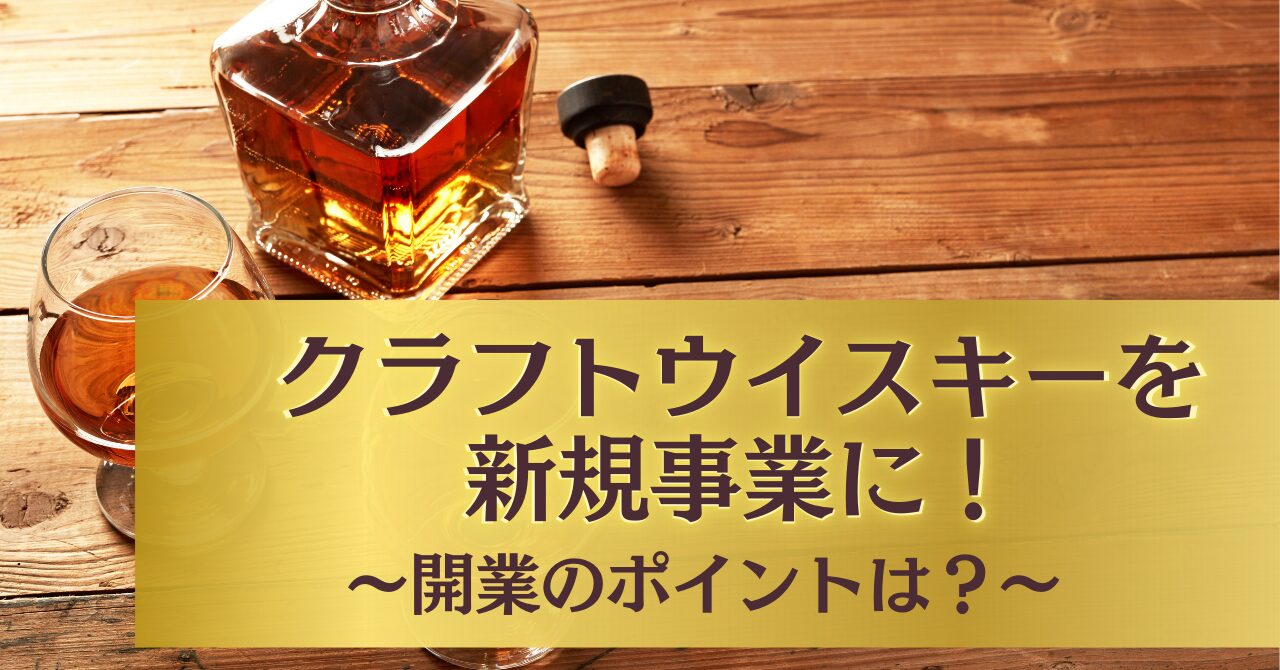最終更新日: 2025年10月25日
■目次
1.クラフトウイスキー事業の魅力
- 世界的ブームの背景
- クラフトウイスキーの魅力
2.新規事業でウイスキー事業を行う基本
- 酒類製造免許について
- 輸出入・販売に関する法的注意点
- ウイスキー事業の予算
3.必要な設備と機材
- 設備と土地について
- ウイスキー事業に必要な機材
4.クラフトウイスキー作りのポイント
- 発酵・蒸留・熟成といった工程
- ブランド差別化につながる味わい
5.まとめ

【この記事を書いた人】
アウグスビール株式会社
取締役COO 村井 庸介
1985年生まれ。慶應義塾大学を卒業して野村総合研究所に入社。
独立後、老舗クラフトビールのアウグスビールの坂本社長と出会い、クラフトビール造りにほれ込み株主となる。
店舗併設型クラフトビール工場やウイスキー蒸留所の立ち上げ支援を行う。
– クラフトウイスキー立ち上げセミナー動画はこちら –
1.クラフトウイスキー事業の魅力

世界的ブームの背景
クラフトウイスキーが世界的に盛り上がる大きな理由は、「個性」や「地域性」を重視する消費者ニーズの高まりと言えるでしょう。
特に日本のウイスキーは注目を集めており、今後も市場が拡大していくことが予想されます。
日本国内ではここ5年間で新規開業したクラフト蒸留所が10か所以上増え、観光客やウイスキー愛好家を取り込む動きが活発化しています。
ウイスキーの新規事業参入は「競合が多いから難しい」というわけではなく、「独自性とマーケティング次第でチャンスが大いにある」といえます。
クラフトウイスキーの魅力
クラフトウイスキー最大の魅力は、テロワールと職人技が創り出す「一点モノ」の味わいです。
たとえば、北海道で採れる大麦と、寒冷地特有の熟成環境を組み合わせた蒸留所は、香り高くスモーキーな風味を持つウイスキーを生み出します。
職人のこだわりが直接消費者に伝わりやすい点もクラフトウイスキーの大きな魅力。蒸留所ツアーやテイスティングイベントを企画し、顧客に製造工程を体感してもらうことで、リピーターや口コミ効果が期待できます。
さらに、地元の農家と連携し、廃棄されるはずだった副産物を飼料や肥料に活用する循環型モデルを用いた蒸留所も注目を集めています。環境配慮やサステナビリティを重視する消費者層から支持を得やすく、ブランドイメージの向上にもなりそうですね。
2.新規事業でウイスキー事業を行う基本
ウイスキー事業に新規参入するには、免許取得や法的手続きを知り、長期的な視点での経営戦略を行うことが肝心です。
酒類製造免許について
- 取得プロセスと要件
- 申請から免許交付まで半年~1年程度が目安。書類不備や生産計画の不明確さなどで審査が長引くこともある。
- 小規模蒸留所でも「年間何千リットル以上の生産見込み」が求められるケースがあり、「マイクロ」すぎる生産計画は受理されにくい。
- 専門家との連携が成功のカギ
- 税理士や行政書士と協力し、酒類製造免許の審査をクリアした後、即稼働できるように設備や人材をあらかじめ手配しておくと、事業開始のタイムロスを最小化できる。
輸出入・販売に関する法的注意点
- 国内販売:直営店からオンラインまで
- 酒税法、食品衛生法、特定商取引法など、複数の法律を並行して遵守する必要がある。
- 海外展開:関税・ラベリング・原産地表示
- 各国の規定(ウイスキーと呼べるアルコール度数や熟成期間など)への適合を確認すること。
- EUや北米の食品衛生基準や消費者保護規制に従い、輸入代理店や専門のコンサルタントを活用する事例が多い。
ウイスキー事業の予算
- 初期設備投資
- 小規模ながら高品質を狙う蒸留所では、ポットスチル1基に数百万円〜1,000万円超、樽1本数万円~十数万円など、必要経費はあっという間に数千万円にのぼる。
- 大型施設を整えようとすると数億円規模になるため、創業時は最小限の設備で実験的に生産を開始し、受注や評判に応じて拡大する段階的アプローチがおすすめ。
- 熟成期間とキャッシュフロー
- ウイスキーは3年以上の熟成を要するケースが多いため、販売開始までの運転資金が必要。
- 一方、ジンやウォッカなど短期間で商品化できる蒸留酒を併産することで、キャッシュフローを確保する事業者も多い。
- 資金調達とリスク管理
- クラウドファンディングを活用し、樽買いオーナー制度や限定リリース先行販売で資金を集める動きが広がっている。
- 投資家の出資を受ける場合、ブランド戦略や収益モデルをしっかりプレゼンすることが重要。仮に規模拡大で失敗した際のリスク分担や契約内容も事前に詰めておく必要がある。
3.ウイスキー事業に必要な設備と機材

設備と土地について
- 水質重視 vs. アクセス重視:失敗を避ける土地選定
- ウイスキーの味わいに直結する水質を最優先するなら、山間部や湧水地の近隣が適しています。ただし、輸送コストや観光客の集客が難しくなるリスクも。
- 都市部に近い立地なら、物件取得費や人件費が高くなりがちですが、見学ツアーやバー運営などで売上を補完できる場合も。
- 建物設備:リノベーションのメリットとデメリット
- 改装可能な倉庫や古民家を選ぶと、初期費用を抑えながらオリジナリティのある空間演出が可能。一方で、耐震性や消防法、排水設備などの改修に追加費用がかさむリスクも存在。
ポットスチル導入のポイント:大きさよりメンテナンス体制
蒸留所の“心臓部”ともいえるポットスチルは、一度導入すると長期にわたり稼働するため、メンテナンスや部品交換の可否が重要。海外製スチルを導入する場合、修理のたびに外国から技術者を呼ぶ必要があるかどうかも検討材料です。
仕込み設備・発酵槽:生産拡大を見据えた設計
仕込みタンクや発酵槽は、将来的な増産を想定して余裕を持った設計をするか、段階的に買い足せるモジュール式にするかが悩みどころです。
小規模生産から始めたい場合は、中古のホーロータンクやステンレスタンクを安価に調達する事例もあり、予算に応じてさまざまな選択肢があります。
樽熟成と倉庫管理:長期保管のリスクをカバー
シェリー樽やミズナラ樽など高額な樽を大量に導入すると、初期投資が一気に膨れ上がるので注意が必要です。クラウドファンディングで樽オーナーを募集し、資金を先に集めてから購入するモデルも一般的になりつつあります。
熟成倉庫内の温湿度管理システムは導入コストが大きい反面、品質を安定させるうえで効果的。倉庫改修や空調設備費を抑えたいなら、自然環境を活かした郊外型熟成も選択肢の一つです。ただし、自然条件が厳しいと熟成速度の予想が難しくなるリスクも伴います。
5.まとめ
ウイスキー事業を立ち上げる際の免許・法規制、必要な設備・機材などを解説してきました。
現在の国内外市場はクラフトウイスキーに対する期待感と需要が高まっています。
もちろん、初期投資や長期熟成期間などのリスクは小さくありません。しかし、少量多品種の生産スタイルや、観光・地域連携を絡めたビジネスモデル、SNSやクラウドファンディングを活用した投資・ファン獲得などの成功例も豊富に存在します。
クラフトウイスキーが持つ「個性」「ストーリー」「地域性」は、大手には真似できない大きな武器です。
アイデアやこだわりを存分に活かし、消費者とのコミュニケーションを深めることで、ウイスキー新規事業は単なる飲料ビジネスを超えた文化的な挑戦となるでしょう。
ぜひ、今回ご紹介したポイントを足掛かりに、新規事業としてウイスキーブランドを育ててみるのはいかがでしょうか。
– クラフトウイスキーの製造をご検討の企業様へ –
クラフトウイスキー蒸留所の立ち上げを検討されている方必見。
実は、マイクロブルワリーとの融合で、小規模でもクラフトウイスキーを造れる方法があります。
しかも、熟成期間中の売上も立てる方法があります。
情報をご希望の方は、まずはマイクロブルワリーの資料をご請求ください。
毎月開催のオンラインセミナーも行っております。
日本各地で開業支援実績があるアウグスビールの『マイクロブルワリープロデュース』で、クラフトウイスキーの立ち上げを検討してみませんか?
※オンラインセミナーでウイスキーの話をご希望の際には、メッセージ欄にご記載をお願い致します。
[資料請求]
[毎月開催オンラインセミナー]