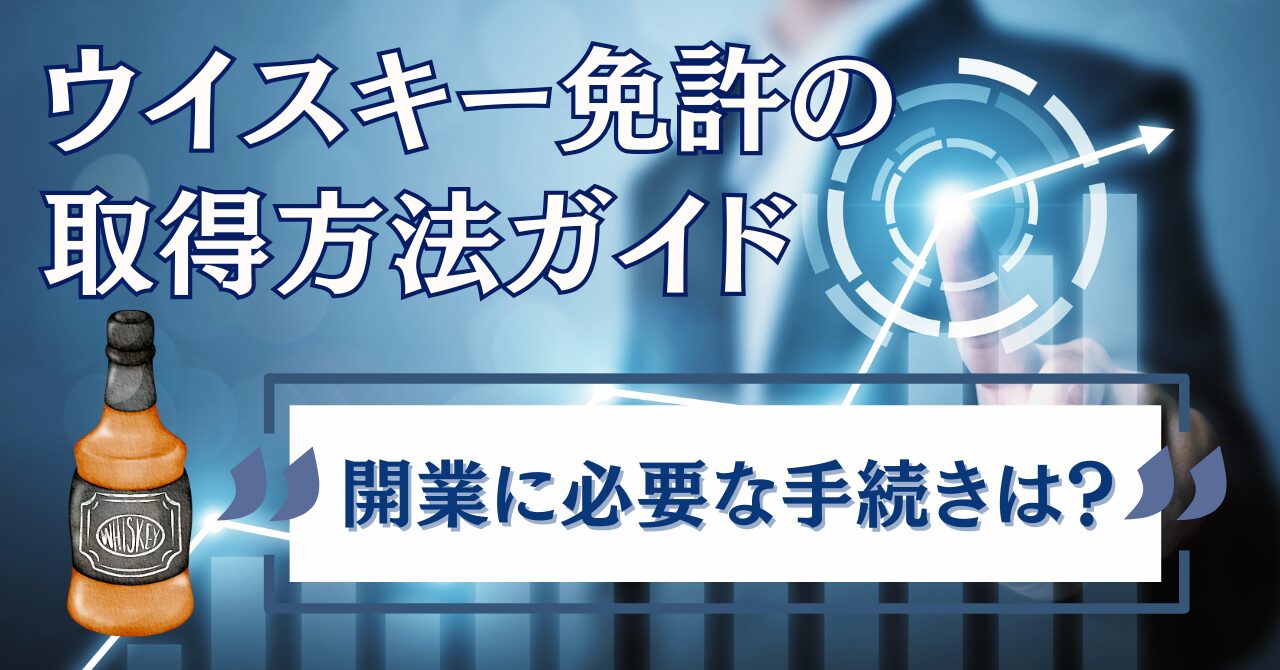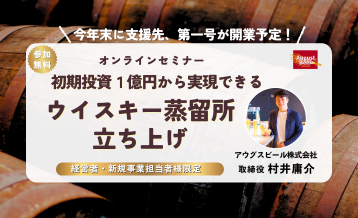最終更新日: 2026年1月12日
◾️目次
1. ウイスキー免許とは?
・ウイスキー製造に必要な「酒類製造免許」
・蒸留酒製造免許の種類(単式蒸留・連続式蒸留)
・クラフトウイスキー製造に必要な免許とは?
2. ウイスキー免許を取得するための条件は?
・年間製造数量の基準(最低製造見込み量)
・経済的要件(自己資金・設備投資・事業計画)
・人的要件(酒税法上の責任者・人的体制)
・物的要件(製造設備・工場構造・環境面の条件)
3. ウイスキー免許取得までの手続きフロー
・事前相談〜申請の流れとスケジュール
・必要書類一覧と記載の注意点
・審査期間と許可が下りるまでの目安
・審査で重視されるポイントと事前対策
4. ウイスキー製造所の立地と施設要件
・立地選定で注意すべき法規制と自治体対応
・建築基準法・消防法との関係と留意点
・工場の面積・構造・導入設備の具体例
・熟成庫の設計・湿度・温度管理の基本
5. ウイスキー免許取得の注意点とよくある落とし穴
・免許が取得できない典型的なケース
・酒税法違反リスクと営業停止の可能性
・「酒類販売免許」との違いと誤解しやすいポイント
6. まとめ

【この記事を書いた人】
アウグスビール株式会社
取締役COO 村井 庸介
1985年生まれ。慶應義塾大学を卒業して野村総合研究所に入社。
独立後、老舗クラフトビールのアウグスビールの坂本社長と出会い、クラフトビール造りにほれ込み株主となる。
店舗併設型クラフトビール工場やウイスキー蒸留所の立ち上げ支援を行う。
– クラフトウイスキー立ち上げセミナー動画はこちら –
1:ウイスキー免許とは?

ウイスキーの製造には、「酒類製造免許」の中でも蒸留酒類製造免許の取得が必須です。
これは、ウイスキーが発酵だけでなく蒸留工程を経て製造される酒類だからです。
ウイスキー製造に必要な「酒類製造免許」とは?
酒類製造免許とは、酒類を製造・販売するために国税庁(税務署)から交付される公的な許可です。
日本国内では、酒税法に基づいて「酒類」と分類されるものを造るためには、この免許が必要になります。
ウイスキーは酒税法上「蒸留酒類」に該当します。
つまり、「発酵」させたものをさらに「蒸留」する必要があるため、通常のビールやワインとは異なる免許が必要です。
蒸留酒製造免許の分類(単式蒸留・連続式蒸留)
蒸留酒類製造免許は、大きく以下の2つに分かれます。
| 種類 | 主な用途 | 蒸留方法 |
|---|---|---|
| 単式蒸留焼酎等製造免許 | 焼酎、泡盛、クラフトウイスキー等 | 単式蒸留器(ポットスチル) |
| 連続式蒸留焼酎等製造免許 | ウォッカ、連続式焼酎、大手メーカーのウイスキー等 | 連続式蒸留器(カラムスチル) |
クラフトウイスキーを作る場合、単式蒸留焼酎等製造免許を取得することが一般的です。
これは「単式蒸留器(ポットスチル)」を使って製造される、風味豊かな少量生産型のウイスキーに適しています。
大手企業などが扱う大量生産型のウイスキーは、効率を重視して「連続式蒸留器(カラムスチル)」を使用します。その場合は「連続式蒸留焼酎等製造免許」が必要になります。
クラフトウイスキーに該当する免許の種類とは?
個人や小規模法人がウイスキー蒸留所を立ち上げる際には、「単式蒸留焼酎等製造免許」を申請するケースが一般的です。
この免許を使って製造できるのは、焼酎や泡盛だけでなく、ウイスキーやブランデーなどの蒸留酒類も含まれています。
ここで重要なのが、「酒税法における製法や定義」に適合しているかを明確に示す必要があるという点です。
つまり、何を、どのような設備で、どのくらいの量作るのかという具体性が求められます。
2:ウイスキー免許を取得するための条件は?

ウイスキー製造免許(正確には「蒸留酒類製造免許」)を取得するには、4つの厳しい審査条件をクリアする必要があります。
それは、「製造数量」「経済的要件」「人的要件」「物的要件」の4本柱です。国税庁はこれらの基準に基づいて総合的に審査を行い、免許を交付するかどうかを判断します。
年間製造数量の基準(最低製造見込み量)
酒税法に基づき、免許取得には一定の年間製造見込み量(=最低製造量)を満たす必要があります。
- 単式蒸留焼酎等製造免許(ウイスキー含む)の最低製造数量は年間6キロリットルです(=約6,000リットル)。
※これは日本全国どこで申請しても基本的には変わりません。
これより少ない量しか製造できない設備や事業計画の場合、「需要がない」「商業性が薄い」と判断されてしまい、免許が下りません。
経済的要件(自己資金・設備投資・事業計画)
免許審査では、継続的に事業を行う財務的裏付けがあるかが厳しく見られます。
主な評価ポイントは以下の通りです。
- 自己資金の有無と金額(目安として最低でも1,000万円以上)
- 設備導入・施設整備に必要な初期投資の計画
- 原材料調達・人件費・光熱費なども含めた収支計画(数年分)
- 事業としての持続可能性・成長性があるか
計画が不明瞭だったり、資金が不足している場合、審査で不許可になることがあります。
特に「ウイスキーはすぐに売上にならない」ため、熟成期間中の資金繰りも含めた計画が必要です。
人的要件(酒税法上の責任者・人的体制)
製造には、法律や酒税管理に関する知識を持つ人材が適切に配置されているかも重要な判断材料です。
- 酒類製造責任者(=代表者や製造管理者)は、製造工程に関する理解が必須
- 酒税管理者の配置(製品出荷量や在庫を正確に申告・管理する役割)
- 経験豊富な技術者・オペレーターがいるか(外部アドバイザーも含む)
国税局からは、「本当に酒税を適切に納税できる体制があるか?」という観点でチェックされます。
物的要件(製造設備・工場構造・環境面の条件)
以下のようなハード面の充実度も免許取得には不可欠です:
- 蒸留器、糖化槽、発酵タンク、熟成樽など、製造に必要な設備があること
- 衛生管理・安全対策がなされた製造所の構造(例:防火構造、防虫対策)
- 工場や熟成庫が周辺の住宅や学校と十分な距離を取っている(騒音・臭気問題)
また、製造場所と熟成庫は物理的に分離されていてもOKですが、それぞれ申請時にきちんと図面を添付して示す必要があります。
3:ウイスキー免許取得までの手続きフロー

ウイスキーを製造するためには、前章で述べた条件を満たしたうえで、正式に「酒類製造免許(蒸留酒類)」を申請する必要があります。
この章では、免許取得までの流れや必要書類、審査期間、通過のためのポイントを詳しく解説します。
事前相談〜申請の流れとスケジュール
免許申請は、いきなり書類を出しても受け付けてもらえません。
まずは所轄の税務署に事前相談を行い、免許申請の意思を伝えるところからスタートします。
一般的な流れは以下のとおりです。
- 事前相談(税務署)
→ 事業計画書や製造内容の概要、製造設備の構想などを提示します。 - 必要書類の準備・作成
→ 計画内容が明確になってから、具体的な申請書類を作成します。 - 正式申請(税務署へ提出)
- 審査・補足対応(国税局)
- 許可・免許交付
スケジュール感の目安としては、事前相談〜申請:1〜3か月、申請〜許可:3〜6か月程度。
全体では半年〜1年ほどかかるケースが多いです。
必要書類一覧と記載の注意点
提出する主な書類は以下の通りです:
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| ① 酒類製造免許申請書 | 申請者情報、製造酒類の種類など |
| ② 製造場の位置図・配置図・設備図 | 住所、構造、設備の詳細を記載した図面類 |
| ③ 製造方法書 | ウイスキーの製造工程を詳細に記載(糖化、発酵、蒸留、熟成まで) |
| ④ 原材料・製造予定数量一覧 | 使用予定のモルトや酵母、製造見込み量など |
| ⑤ 事業計画書・収支計画書 | 3~5年分の売上・原価・利益計画など |
| ⑥ 資金調達計画書 | 自己資金・借入・補助金の明細と資金繰り計画 |
| ⑦ 役員名簿・経歴書 | 経営陣の経歴と責任者の能力を示す |
ポイントは、「情熱」だけでなく、「事業として実現可能であること」をロジカルに説明することが求められます。
国税側が不明点を持つと補足説明や修正依頼が入り、審査が長引く要因にもなるので、最初の書類精度が非常に重要です。
審査期間と許可が下りるまでの目安
申請してから免許の可否が決定するまでの期間は約3〜6か月です。
審査期間は案件の規模・内容・提出書類の完成度によって異なります。
審査中に「補足資料の提出」や「追加説明」が求められるケースが多く、事前に税務署との関係を築いておくことで対応がスムーズになります。
審査で重視されるポイントと事前対策
以下は、国税局が審査の際に特に重視している項目です。
- 製造数量が最低基準(6kL)を超えているか
- 資金繰りが適切に設計されているか
- 設備や工場が法令に適合しているか
- 税金管理や納税体制が整備されているか
- 代表者・製造責任者が信頼できる経歴・能力を持つか
事前相談時にこれらの点を明確かつ論理的に説明できるかどうかが、審査通過率を大きく左右します。
4:ウイスキー製造所の立地と施設要件

ウイスキー製造免許を取得するには、製造に適した土地・建物・設備を整えることも必須です。
審査に通過するためには、酒税法や建築法規に適合する構造であることはもちろん、地域住民との共存や安全性にも配慮した計画が求められます。
立地選定で注意すべき法規制と自治体対応
蒸留所の立地は、「空き倉庫や古民家を使えば良い」という単純なものではありません。
以下のような観点から選定する必要があります。
- 用途地域の確認(都市計画法)
→ 工場用途として使用できる地域か、事前に自治体に確認が必要です。住宅専用地域では認可されない場合も。 - 臭気や排水処理への配慮
→ 発酵・蒸留工程では香りが発生するため、住宅密集地では住民トラブルの懸念があります。 - 交通アクセスと物流性
→ 原料搬入・製品出荷のため、トラックがアクセスしやすい立地が望まれます。
地方では「空き施設の利活用」に積極的な自治体も多いため、地域振興や産業支援を目的とした補助金・優遇措置が受けられることもあります。
建築基準法・消防法との関係と留意点
蒸留所は火気やアルコール類を扱うため、以下の法規制にも十分注意する必要があります。
- 建築基準法:用途変更や改修を行う際には建築確認申請が必要です。
- 消防法:蒸留工程で使用するエタノールは可燃性液体に該当し、特定防火対象物の基準を満たす必要があります。
→ 消防署への事前相談が推奨されます。
例:
・一定量を超えるアルコール類の貯蔵には、防爆仕様の設備や消火器・排気設備などが必要
・火災報知器、誘導灯の設置義務も発生
特に古民家や木造建築を使う場合、改修コストが想定より大きくなるケースが多いため、計画段階で精査しておくことが重要です。
工場の面積・構造・導入設備の具体例
製造所として適正と認められるには、以下の条件を満たすことが推奨されます。
- 面積目安:100〜300㎡以上が一般的(製造+貯蔵+作業動線を確保)
- 構造:コンクリート・鉄骨・不燃素材が望ましい
- 動線設計:原材料搬入 → 糖化・発酵 → 蒸留 → 樽詰め → 出荷 の流れが明確で、安全に作業できる配置
主な導入設備:
| 設備 | 用途 | 注意点 |
|---|---|---|
| 蒸留器(ポットスチル) | アルコール抽出 | 材質・容量・熱源により法規制あり |
| 糖化槽・発酵タンク | モルト糖化・酵母発酵 | 温度管理が重要 |
| 冷却装置・配管設備 | 蒸気冷却・アルコール抽出後処理 | 冷却水の管理が必要 |
| ボイラー・熱源機器 | 蒸留・殺菌に必要 | 火気設備として消防法対象 |
熟成庫の設計・湿度・温度管理の基本
熟成庫はウイスキーの品質を左右する極めて重要な空間です。
ポイントは下記のとおりです。
- 構造:外気の温度差を活かせる木造または断熱構造が理想
- 広さ:免許取得時に最低でも50樽(200L×50本=10,000L)程度は熟成可能であることを想定
- 温湿度管理:目安として温度15〜25℃、湿度60〜80%
- 安全性:アルコール揮発による引火防止のための換気・防火対策が必要
熟成庫が別建物の場合でも、「製造場の一部」として免許申請に含める必要があります。図面や写真付きで提示しましょう。
5:ウイスキー免許取得の注意点とよくある落とし穴

酒類製造免許の取得は、「書類を整えれば誰でも取れる」ものではありません。
高いハードルと厳格な審査基準が設けられており、些細な不備でも不許可となるケースがあります。
この章では、クラフトウイスキー開業を目指す方が特に気をつけたい注意点と、よくある失敗例を解説します。
免許が取得できない典型的なケース
以下のようなケースでは、審査段階で不許可になることが非常に多いとされています。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 年間製造見込み量が6kL未満 | 酒税法上の最低製造量に満たない(=営利性がないと判断) |
| 資金計画が不明確 | 自己資金・収支計画の整合性がなく、継続可能性に疑問 |
| 設備が未設置または未確定 | 実体のない「机上の計画」とみなされる |
| 住民との合意が不十分 | 苦情リスクを理由に地域と軋轢があると判断されやすい |
| 責任者が酒税法・製造知識に乏しい | 管理不全・納税リスクとみなされる |
特に「とりあえずやってみたい」「自宅で試験的に…」というアプローチでは、ほぼ確実に不許可となります。「事業」としての実現可能性・継続性・安全性が求められるのです。
酒税法違反リスクと営業停止の可能性
免許取得後も、適切な運用が行われていないと営業停止処分・免許取消・罰則の対象になります。
実際に過去には、以下のような違反で処分が行われた例もあります。
- 製造量や在庫の虚偽申告(酒税法違反)
- 無許可エリアでの熟成や瓶詰(施設外での工程は登録必須)
- 帳簿不備や税務申告漏れ
これらは悪意がなくても、知識不足や運用ミスでも発生するリスクがあります。
そのため、免許取得後も専門家(税理士・行政書士)や顧問サポーター、専門家と連携する体制が重要です。
「酒類販売免許」との違いと誤解しやすいポイント
初心者が特に混同しやすいのが、「酒類製造免許」と「酒類販売免許」の違いです。
| 項目 | 製造免許 | 販売免許(小売・通信販売) |
|---|---|---|
| 管轄 | 国税庁(税務署) | 都道府県(都道府県税事務所等) |
| 内容 | ウイスキーを造るための免許 | 一般消費者に販売するための免許 |
| 種類 | 単式蒸留・連続式蒸留など | 一般小売、通信販売、料飲店向けなど |
| 両方必要か? | Yes(製造して自社で売る場合は両方必要) |
つまり、「ウイスキーを造って売りたい」場合は製造免許と販売免許の両方が必要になります。
製造免許が下りたあとに販売許可申請を行う流れが一般的です。
また、販売免許にも通信販売専用(ECサイト販売)や飲食店限定小売など複数の種類があるため、自社の販売方法に応じた申請が求められます。
6:まとめ
クラフトウイスキーの蒸留所を立ち上げるために必要な「ウイスキー免許(=酒類製造免許)」の取得には、明確な基準と慎重な準備が求められることがわかりました。
ウイスキー製造免許の取得には、法令遵守・計画性・資金力・専門知識といった「堅実さ」が求められます。
しかし同時に、審査官が見ているのは、その事業に本当に「未来」があるかどうかです。
つまり、「売れる見込みがあるのか?」「地域に貢献するのか?」「飲み手を幸せにできるか?」といった、“ビジョン”や“情熱”も免許取得の鍵となるのです。
本記事が、ウイスキー製造という夢への第一歩を踏み出す皆さまにとって、有益な道しるべとなれば幸いです。
– クラフトウイスキーの製造をご検討の企業様へ –
クラフトウイスキー蒸留所の立ち上げを検討されている方必見。
実は、マイクロブルワリーとの融合で、小規模でもクラフトウイスキーを造れる方法があります。
しかも、熟成期間中の売上も立てる方法があります。
毎月開催のオンラインセミナーも行っております。
日本各地で開業支援実績があるアウグスビールで、クラフトウイスキーの立ち上げを検討してみませんか?